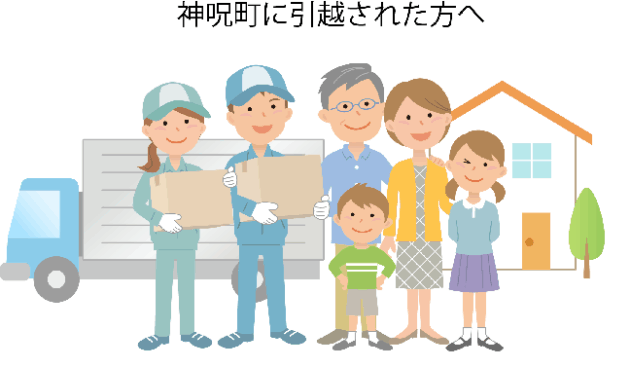神呪町(かんのうちょう)って?
中世に甲山のふもとにあった神呪寺が移設されていたことによります。
神呪寺(かんのうじ)は、淳和天皇妃真井御前(如意尼)が
弘法大師の力を借りて建立したと言われているお寺で
お寺上の山が甲山です。通称・甲山大師と呼ばれています。
淳和天皇(じゅんなてんのう、786年〈延暦5年〉- 840年6月11日〈承和7年5月8日〉)は、日本の第53代とされる天皇(在位:823年5月29日〈弘仁14年4月16日〉- 833年3月22日〈天長10年2月28日〉)。諱は大伴(おおとも)。西院帝ともいう。
桓武天皇の第七皇子。母は藤原百川の娘の旅子。平城天皇・嵯峨天皇の異母弟。
織田信長によって焼き払われた後、一時期ふもとに移っていたことから、甲東園駅の西側に「神呪村(現在の神呪町)」ができたとされています。
神呪(かんのう)は「神の呪い」とも読めますが、本来は「じんじゅ」と読み、真言(仏様の言葉)を意味します。
神呪寺は甲山山麓にある仏教寺院で、甲山を神の山とする信仰があり、この寺を神の寺(かんのじ)としたことが名前の由来と言われています。
神呪寺は真言宗御室派別格本山で、別名甲山大師とも呼ばれています。
神呪寺の境内の本尊・如意輪観世音菩薩坐像は重要文化財で、日本三如意輪観音の一つとされています。また、大師堂に祀られている弘法大師像は、厄除大師として信仰されています。
桜と新緑の名所でもあり、境内からは美しい市街が一望できます。
“神様が呪う町”とも読めてしまい一見怖い名前ですが、この地名の由来は“神呪寺”という立派なお寺。
住職さんによると“神呪”は“神の呪い”ではなく、“神様が与えてくれるありがたい呪文”なのだそうです。
昨日、西宮・神呪寺かんのうじが桜紋さくらもんであることをご紹介しました。そこで、この寺を開山した如意にょいさまという尼僧にそうについてお話をしたいと思います。
彼女は平安時代の始め、天あまの橋立はしだてにある籠神社このじんじゃ(真井神社まないじんじゃ)の宮司・海部あまべ氏のもとに生れ、厳子うついこと名づけられました。籠神社は元伊勢もといせ(伊勢神宮のふるさと)とまで呼ばれる由緒ある神社です。また海部氏は今なお直系がつづく日本最古の家系図(国宝)を保有しています。
十歳にして京都・六角堂に入り、如意輪観音にょいりんかんのんを礼拝らいはいして真言を唱える日々を送っていました。まだ年端としはも行きませんでしたが、天性の気品に満ちた美しい女性であったと思われます。そして二十歳のおり、当時の皇太子であった淳和天皇しゅんなてんのうに見初みそめられ、第四妃として宮中に迎えられました。宮中では「真井御前まないごぜん」と呼ばれ、帝みかどの寵愛ちょうあいを一身に集めました。しかし、後宮こうぐうたちの激しい嫉妬しっとに無常を感じ、二十六歳で二人の侍女と共に宮中を退出したのでした。それは西宮に甲山かぶとやまという仙境があり、寺院を建立するにふさわしい峰であるとの夢告むこくがあったからともされています。
天長五年十一月、妃はお大師さまを甲山に招き、如意輪観音の修法を依頼しました。また翌年五月には、役の行者えん ぎょうじゃを慕って女人禁制の大峰山おおみねさんにも登っています。いったい、どんな手立てを講じたかはわかりませんが、男まさりの一面もあったのでしょう。また、大峰山の人たちも驚いたに違いありません。
天長七年七月、妃はお大師さまによって傳法灌頂でんぼうかんじょうへの入壇にゅうだん(阿闍梨あじゃりになる儀式)が許されました。さらに、桜のご神木しんぼくをもって如意輪観音像の奉彫も依頼しました。お大師さまは妃や侍女たちが真言を唱える中、妃の身長と尊容そんように合わせて完成させました。これが神呪寺の本尊・如意輪観音です。
天長八年十月、お大師さまを導師に神呪寺の落慶法要らっけいほうようを挙行し、自身の法名を如意にょいとしました。また二人の侍女も尼僧となり、その法名は如円にょえん・如一にょいつと記録されています。昼夜を問わず念誦ねんじゅをくり返していたそうで、これが寺号・神呪寺の由来でありましょう。
承和じょうわ二年三月二十日、すなわち、お大師さまがが入定されるまさに一日前、如意尼ははるかに高野山を礼拝しつつ、如意輪観音の真言を唱えながら静かに息を引き取りました。時に三十三歳でした。
如意尼こそはお大師さまの人生においてご母堂以外、深い絆きずなで結ばれた唯一の女性です。私はかねてより籠神社と神呪寺に参りたいと念願していますが、未だに果していません。特に神呪寺で等身大のその尊容にお目にかかれることを、今から楽しみにしています。
そして最後に申し上げますが、今日のブログに特に心引かれた方は、お大師さまとも如意尼とも、籠神社とも神呪寺とも、また私とも特にご縁の深い方であると思います。そう、思いますよ。
六甲山と甲山は一体になっているように見えますが、実は成り立ちが違います。六甲山は地殻変動で隆起してできた山ですが、甲山は火山です。1200万年前という大昔に噴火して、そのあと火口付近の硬い部分だけが残ったのがいまの甲山なんだそうです。
また「甲山」という名前の由来は諸説あります。神功皇后様が平和を祈念して金の兜を埋めたから。昔、大きな松の木が二本生えていて、山の形が兜に似ているから。「神の山」(こうのやま)が「甲の山」になって「甲山」になった。どれも本当っぽいですね。
ちなみに六甲山は、むかし大阪市の大部分がまだ海だった頃、上町台地辺りから眺めて「西の海の向こうの山」が「むこう山」を経て「六甲山」になった、という説があります。「武庫川」(むこがわ)もその流れで名前が付いたのだとか。この辺り、本当はどうなのかわかりませんが、ちょっと面白いですね。
さて、神呪寺の名前の由来ですが、これは「神を呪う」なんていうこわい意味ではもちろんありません。そもそもこの「呪」というのは「呪文」の「呪」という意味です。「神の呪文」ですね。神呪寺さんのリーフレットによりますと、「甲山を神秘的な神の山として信仰したところから、この寺を神呪寺(神のような不思議な強い力のある寺)と名付けられました。」とあります。また、「神呪(かんのう)とは般若心経にある神呪(しんじゅ)で、真言という意味があります。」とも書かれています。
神呪寺さんは真言宗御室派別格本山、別名甲山大師ですから、こう考えると神呪という名前はごく自然に思えますね。
甲山の中腹に位置する神呪寺。阪急甲東園駅と門戸厄神駅の間に位置する神呪町。同じ「神呪」と名の付く「寺」と「町」がなぜ離れているのか、不思議に思ったことはありませんか。神呪寺は災難に見舞われ、一時期神呪町付近に下山していたことがあり、地名として残ったと言われています。
「神呪寺仁王門」は、文化元年(1804年)に神呪寺第63世寛眼が建立した山門で、西宮市指定文化財となっています。左右の屋根を段違いに掛けた珍しい形式で、旧地に復興した寺院の象徴的な建物です。
平安時代に甲山に建立された神呪寺は、戦国時代に織田信長が荒木村重を追討した有岡城の戦いで、信長により焼き打ちにされました。さらに豊臣秀吉の太閤検地で寺領の大半を没収されてしまいます。堂塔も寺領も失った神呪寺は山を降り、法灯を継いでいきました。江戸時代中期、歴代住職による甲山への復帰運動がようやく実を結びます。そして荘厳な造りの仁王門を完成させたのです
荒木村重(あらきむらしげ)は、織田信長に仕えていた戦国武将。 織田信長の家臣として摂津国(現在の大阪府北中部、及び兵庫県南東部)平定や、石山本願寺攻めで活躍しました。
追討(ついとう)賊徒(ぞくと=ぬすびとの仲間)などを追いかけて討ちとること
有岡城の戦い(ありおかじょうのたたかい)は、天正6年(1578年)7月から翌天正7年(1579年)10月19日にかけて行われた籠城戦。織田信長に帰属していた荒木村重が突然謀反を起こしたことに端を発する。伊丹城の戦いとも呼ばれている